
猫と犬の祖先は一緒。動物の母・ミアキス
犬と猫の共通する祖先といわれている「ミアキス」は、
約6500万~4500万年前に生息していたとされる動物です。

ミアキス想像図・Newtonより
ラテン語で「動物の母」という意味を持つミアキスは
主にヨーロッパ大陸などの森に分布し、体長は約30センチ、
スリムな胴体に長い尻尾と短い脚が特徴で、
イタチに似た姿であったと考えられています。
このくだりは前回の
と同じですが、今回は、猫の祖先と進化について書いていきたいと思います。
森林に残って暮らしていたミアキスが猫の祖先に
猫の祖先は、ミアキスの時代から森林で生活し、
長い間そこから出ることはありませんでした。
森林では身を隠すことが簡単にできます。
そこで、木陰に隠れながら獲物を待ち伏せして、
獲物が通りかかったとたん、優れた瞬発力で獲物を仕留める、
という方法の狩りが有効です。
草原へ移動せず、森林に残って暮らしていたミアキスは「待ち伏せ型ハンター」として
後に猫の祖先へと進化していきました。

Scientific americaより
森に隠れて敵から身を守り、時には獲物を狩るために
足の先端から出し入れできる爪はさらに鋭く発達しただけでなく、
元気のよい獲物をしっかりとホールドするため、また、森林生活で木に登るために、
犬と違って手首を回転させ器用な動きをすることが出来るようになります。。
獲物に飛び掛かって瞬時に仕留めるために、柔らかく強靭な後ろ足の筋肉が発達しましたが、
反対に犬のような持久力はあまりありません。
瞬発力や聴覚、木々を移動するための優れた平衡感覚や
小さくてしなやかな体など、猫へと進化していく能力が身についていきました。
猫の起源
私たちが現在一緒に暮らしている猫(=イエネコ)の祖先は
「リビアヤマネコ」という種であったと言われています。

リビアヤマネコは現在も北アフリカや
アラビア半島の砂漠地帯に多く生息しています。
リビアヤマネコは英語で「アフリカン・ワイルドキャット」や
「デザートキャット」と呼ばれています。
「リビア」は北アフリカにある国の名前で、
「デザート」は砂漠という意味ということから、
それぞれ生息地が由来の呼び名であることがわかります。
リビアヤマネコの体型はスリムで、
現在のキジトラにも通じるところのある模様や色をしています。


340万年前と言う気の遠くなるほどはるか昔に枝分かれしたとは思えないほど、
現在の猫と同じ特徴を持っています。
ところでベルクマンの法則って何?
犬の進化の話から時折出てくるベルクマンの法則。
ベルクマンの法則とはドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマンが
1847年に発表したものであり、
「恒温動物においては、同じ種でも寒冷な地域に生息するものほど体重が大きく、
近縁な種間では大型の種ほど寒冷な地域に生息する」というものである。
これは、体温維持に関わって体重と体表面積の関係から生じるものである。wikipediaより
同じくアレンの法則
アレンの法則は、ジョエル・アサフ・アレンにより1877年に発表された法則であり、
大まかにいうと寒冷気候に適応した動物は、
温暖気候に適応した動物よりも手足や体の付属器官が短いというものである。
より具体的には、恒温動物の体の表面積対体積比は
それらが適応する生息地の平均温度により変化する
(すなわち、その比は寒冷気候では低く、温暖気候では高い)というものである。wikipedhiaより
ベルクマンの法則がわかりやすいのはクマ。


群馬県自然史博物館より
また。アレンの法則がわかりやすいのはキツネであると言われています。


群馬県自然史博物館より
犬や猫もこのベルクマンの法則、アレンの法則に基づいて、
個体の大きさや特徴が変わります。
ベルクマンの法則・猫と猫科の動物
大型のネコ科の動物たちは、
ベルクマンの法則を受けず、アフリカなどの温暖な地で大型化していると思われがちですが、
猫とは食肉目ネコ科ネコ属に分類される動物です。
主に猫という言葉で表すものはイエネコであり、
その他のライオンやトラなどは猫とは呼びません。

北海道大学理学部
猫、とは呼ばないものの、虎などの固有種で見ると、
アムールトラ (Panthera tigris altaica) の体重は180-300kgほど、
ベンガルトラ(Panthera tigris tigris)は180-258kgほど、
スマトラトラ(Panthera tigris sumatrae)は100-140kgほど。
とベルクマンの法則に基づいた体の大きさになっています。

最大の猫、メインクーン
メインクーンとはアメリカのメイン州が名前の由来で、
最大120センチにもなる同州公式の猫として認識されている種類です。

あれ?ベルクマンの法則は…?と思われるかもしれませんが、
メインクーンやノルウェージャンフォレストキャットも、
元々は寒冷地を生息地としていた猫です。

長く交配を続け、現在の品種になっていますが、
元は同じ大型の猫。ブリーディングによって、アメリカ原産と言う事になっています。
最小の猫、クロアシネコ
世界最小のクロアシネコは、成獣になっても1.6キロと非常に小さく、
現存する猫の中では世界最小と言われています。

wikipediaより
クロアシネコは、アフリカ原産。ベルクマンの法則にのっとって、体は小さく、
アレンの法則のまま、耳は大きく、マズルは低めになっています。
同じ母を持つ犬と猫の違い・まとめ。
元々は同じミアキスと言う猫の原種を祖先とする犬と猫。
人の属するホモサピエンスの起源は40~25万年前と言われていますから、
わたしたち人には想像すらできないはるか昔から
環境に適し、進化を繰り返してきました。
地球と言う単位で見ると、人の先輩に当たる犬と猫。
わたしたちはもっと、犬や猫を敬い、
仲良く暮らしていかなくてはなりませんね。
今日のヒメちー
やはり猫は世界の王…。
皆さん、猫を崇め奉るのですよ。

ただねぇやんの話は長くって…
ふあああ~~

あ~~~~

飽きちゃうんですよね…。

ヒメちーはなにかちょっと誤解しているようだけれど、
似ても似つかない猫と犬。はてはクマも同じ祖先をもつとは。
やっぱり猫の時代…来た?










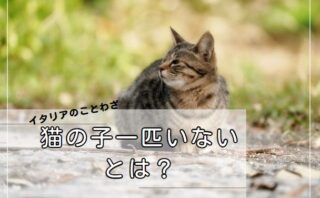












コメント