
犬と猫の舌の動かし方の違い
犬も猫も、ひとのようにコップをもって、ぐいぐいとお水を飲んことはしません。
舌で水をすくい取り、舐めとるような水の飲み方をします。
水の飲み方を見ていると、ひとの舌よりも器用に動く舌に感心します。
ひとも、犬も猫も、舌は表面を粘膜で覆われていますが、
内部は筋肉でできているのでかなり自在に動かせます。
同じように「すくい取る」方法で水を飲みますが、
犬と猫ではその舌の動かし方が大きく違うのです。
猫は水を飲むとき、舌先を「J」の形にして先だけを水につけ、
高速で引き上げる動作をくり返します。
対して犬は、舌を裏側に丸めて勢いよく水をすくい上げて飲みます。

同じ、「舌でなめとる」という動作なのに、
全く違っていて面白いです。
スローモーションにしたGIF画像です。

犬は激しい。
猫は静か。
これは犬と猫の見た目のイメージにも当てはまる気がします。
犬はワイルドに野を駆け回り、
猫は縁側で日向ぼっこをする。
実際、犬や猫と暮らしてみると、このイメージは全く異なるものだと理解できますが、
改めて水の飲み方を見てみるとその違いはイメージ通りであることに驚きますね。
猫は水を飲まないは俗説
猫やウサギは水を飲まない生き物である。
長い事そう信じられていたそうです。
コアラやカンガルーネズミ、ラクダなど、
水を飲まずに生きられる生き物がいますが、
「コアラ」という名前は、オーストラリアの先住民族アボリジニの言葉で
「水を飲まない」の意味。
コアラは水分の多いユーカリの葉で水分を補給しており、
水を直接飲むことは稀であることからそう言われますが、
極度の脱水状態にある時は水を飲むことがあるそうです。

カンガルーネズミは水の少ない砂漠で生きる生き物。
砂漠で生き延びるために、種子から水分を摂取しているそうです。
ラクダは水を飲まずに数週間生きられるといわれており、
これは一度に大量の水を飲むことができ、
体に貯蔵することができることからそう言われるようになったのだとか。
寒い冬が終わり、夏はまだであるものの、
気温は高くなり、知らず知らずのうちに体内の水分が失われてしまう季節がやってきました。
脱水症状と言うと、夏場を思い浮かべがちですが、
実は5月6月の脱水症状はとても多いのだそう。
ひとはのどが渇いた、と感じた際には
約2パーセントの水分が失われているのだそうです。
犬や猫も同じ。
のどが渇いたサインを見逃さず、上手に水分補給してあげましょうね。
今日のヒメちー
猫は孤高の生き物です。
地べたにしゃがんで水を飲むことはしません。

あー、はいはい。
またそういう、わけのわかんない事言っちゃって。
素直に「お水ちょうだい」って言えばいいのに。
良きに計らえ、です。

ヒメちーはフードボウルのお水はめったに飲まない。
これは子供の頃、普通のフードボウルでお水をあげていたんだけれど、
あんまり水を飲まない子だった。
わたしが飲むコップの方が気になるらしくって。
コップであげるようになったらよく飲むようになったのよね。

あ、もちろん、わたしたちが飲むコップとは分けていますよ。

ちろっ。

なんでお水飲むところ、撮影されてるんでしょうね…。
気になります。

ペロペロペロ…。

う~ん。
舌の動きを撮影したかったんだけどなー、無理だった―。








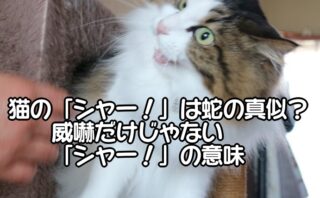













コメント