
オスメスはっきりしている生き物
ひとはオス(男)とメス(女)は見た目からすでに大きな違いがあります。
ところが動物界では見た目での性別の区別がはっきりしないものが。
猫もその一つです。

三毛猫を除いて遺伝子的配列で見た目に大きな差はありません。
骨格がしっかりしている、顔が大きい、目つきが鋭いなどの
うっすらとした特徴はありますが、これには個体差があります。
優しい顔立ちのオスや、険しい顔立ちのメス、など。
オスとメスで外観に違いがあることを、「性的二型」と言います。
性的二型(sexual dimorphism)とは、生物の性別によって、
生殖器以外の形質(体格、角、羽の色など)が異なることを指します。
オスメスが見た目ではっきりと認識できる動物、と言うと
ライオンを思い浮かべることができます。

そう、ライオンは、オスにはたてがみがあり、メスにはない。
ニワトリは、頭の上にあるトサカと、顎からのどにかけてある肉垂で区別できます。

色彩の違いでなら、キジ、ウグイス、

クジャクの尾羽オシドリの羽色(オスが派手)キジの羽色(オスが派手)、

角の違いでなら、シカが挙げられます。

鹿を含むウシ科の動物にはオスだけが角を持つ種は多くいます。
昆虫類なら、カブトムシ、クワガタなど、
角のある無し、あるいは角の大きさで一目でわかるものもあります。
シルバーバックのほか大きさで有名なのはゴリラ、
それにアシカ、ゾウアザラシ、オットセイなど海獣類。
ニホンイタチ:オスはメスの3倍ほど大きくなっています。
人を含むオスメスの違いがはっきりしている動物は
・異性を見つけるときに視覚に頼るかどうか
・異性が選ぶ基準が見た目重視のため特別な進化を遂げている。
この2点が大きく関係しています。
犬、猫の場合は視覚よりも発情期のフェロモン、つまり嗅覚が重視されます。
そして同じ哺乳類でも視力がほぼ退化したモグラは
オスメスの見分けが非常に難しくなっています。
一方、ライオンは独身のオスはメスの群れと離れて暮らし、
メスがいる集団に自ら近づきオスのボスと闘い勝利しなければ
プライド(群れ)の頂点に立てません。
そのため視覚でオスメスを見分けることが必要となります。
鳥の審美眼は人間並み?
美しい羽根を持つことで有名な孔雀の場合は
鳥類という視覚の良さに加えてメスがオスのビジュアルで選びます。

そのため、より雌に選ばれるために美しく進化してきました。
「選ばれる側の性別」がより美しくなる傾向にあります。
多くの鳥類は武器、飾り、色、ダンス、匂い、
歌による求愛(さえずり)がよく観察されています。
鳥類のメスの審美眼はヒトに近いとも言われています。
「メスによる選り好み」は19世紀、イギリスの自然科学者で、
進化論の提唱者として最もよく知られているダーウィンが唱えました。

ダーウィンが唱えた「メスによる選り好み」の説は、
当時なかなか認められませんでした。
オス同士が競争する。その競争は激しく、勝ち残った強いオスがメスを勝ち取る。
そういうことが起こるから、オスの体が大きくなったり、角が生えたりする。
それにはすぐに納得を得られたのですが、
きれいな羽やその類のものが、メスが選ぶからそうなったという意見には、
19世紀のダーウィンの時代の人々は誰も賛成せず、「そんなはずがない」と否定したのです。
否定の根拠については、当時の論争を見るとひどいことがたくさん書かれています。
「選り好みをするような知力が、メスにあるはずがない」とか、
「メスの好みほど気まぐれなものはない。そのような気まぐれでオスが変わってたまるか」など、
ご自分の経験から言っているのかと疑われるような、
とても生物学的なものとは思えない議論がたくさんありました。
しかし、決定的だったのは、メスが本当に選り好みをしているということを、
なかなか立証できなかったことでした。
ダーウィンから100年以上の1990年代、
「メスは選り好みをしている」ということが示されるようになりました。
ちょっと残酷な実験ではありますが、
いろいろな鳥や魚など長い尻尾を持つものの尻尾を半分に切り、
切り取った半分を別のオスの尻尾に貼り付けて、
極端に長い尻尾を持つオスと、半分まで短くしたオスを作る。
雌はどっちに来たかというと、長い方に来たというのです。
そういう種類の実験がたくさん行われ、
オスはメスに選ばれるような長い尻尾や派手な形質を持っていることが
本当に実証されてきたのです。
さえずりについてもそうです。とても美しい声を出す鳥はたくさんいますが、
さえずらないオス鳥よりもさえずるオス鳥の方へ、たくさんのメスがやって来る。
あるいは、さえずりが複雑で美しいオスほど早くメスがやって来る。
さえずりのレパートリーが広く、いろいろな歌い方をするオスほど、
メスがたくさん来て、たくさんの子どもを残す。
そのような実験結果が出、十分に証拠が挙げられましたので、
今では「メスが選り好みをしている」ということは確かなことなのです。
また、力強さ、喧嘩の強さが「選ばれる理由」になる生き物もいます。
力の強さは、動物の性選択において、
オスがメスに選ばれる上で重要な役割を果たします。
特に、雄性淘汰(性選択)が強い動物種において、
力の強さは競争において優位性を生み、
より多くのメスと交尾する機会を得る可能性があります。
例えばシカの角の大きさ、力強さは
オス同士の争いを勝ち抜き、メスを確保するための武器として発達しました。

角の大きさや強さは、オスが優位性を示し、メスから選ばれる要因となります。
ライオンのたてがみは、オス同士の争いを避け、
メスに好感を与えるための装飾として発達しました。

たてがみの大きさや濃さも、オスの健康状態や優位性を表現し、
メスに選ばれる要因となります。
鳥の飾り羽は、オスがメスにアピールするための装飾として発達しました。
羽の色や形は、オスの健康状態や遺伝的な質を示す情報として、
メスに選ばれる要因となります。
魚の体色、昆虫のダンスなど、様々なオスの動物が性選択において、
自身の外見や行動を変化させ、メスに好感を与えるよう進化しています。
これらの例は、力の強さや装飾が、オスの競争力を高め、
メスに選ばれる可能性を高めることを示しています。
雄性淘汰が強い動物種において、力の強さはより多くのメスと交尾する機会を得る上で
不可欠な要素となっているのですね。
今日のヒメちー
どの生き物も、子孫を残すことは大事なことですものねー。

ヒメちーは避妊手術をしてしまっているので子孫は残せない。
それについてはヒト
の側の勝手な都合で申し訳ないと思ってるわ。
いえ、大丈夫です。
猫の世界はなかなか大変なのです。
猫もメスの側に選ぶ権利があると言われてはいますが、
体の大きさやその他によって、望まぬ妊娠を強いられることもあります。

どの世界も、屈強なオスは自分の遺伝子を残したいと思うものですから。

ヒトの世界はオスを選ぶ基準は見た目ですか?力強さですか?

ヒトも太古の頃はたくましさとか狩りの上手さとかが
決め手だったかもしれないけど、今は複雑よねー。

「好みは10人10色」とも言うしね。
見た目だったり、財力だったり、
そういうのじゃなくって優しさとか?
まあ、いろいろよね。

ヒメはおこもりが上手な人がいいですね。
こうしてパジャマを差し出してくれるような人が…。

結局、ヒトとか猫とかの種別や
性別の垣根超えてままちゃんがスキーってことね。


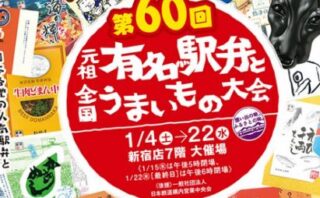

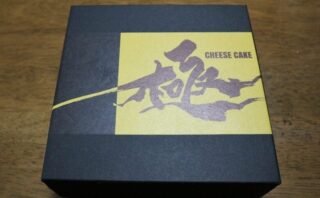

















コメント