
夫婦別姓導入しなければ…500年後みんな「佐藤さん」に
現行、婚姻の際には、男性、女性の
どちらかの姓を選択することになっています。
日本は世界で唯一、
結婚したら夫婦が必ず同姓を名乗ることが義務づけられているのです。
東北大高齢経済社会研究センターの吉田浩教授の試算によると
約500年後の2531年、日本人の全員の名字が「佐藤さん」になるかも――。
という、エープリルフールのウソのような推計がでました。
別姓について考えてもらうキャンペーン
日本では、毎年約50万組が結婚しており、
どちらかの姓を選択するため、その分、名字の数は減っています。
明治時代以降、日本にはおよそ13万種類の名字が誕生しました。

すでに5万種類が5軒以下の「絶滅危機」にあり、
「かつては子どもの数が多かったので子の誰かが名字を引き継いでいたが、
少子化が進み、名字を残すことがむずかしくなってきている」ということが理由のようです。
このまま選択的夫婦別姓を導入しない場合に、
国内の名字の数がどう変化するか。の一環で、
吉田浩教授が試算したところ、そんな結果が出たということです。

東北大高齢経済社会研究センターの吉田浩教授によるシミュレーション結果=発表資料から
吉田教授によると、現在、国内で最も多い名字は「佐藤」で、
全体の約1.5%を占める。
「このまま夫婦同姓のルールのもとで結婚が繰り返されていくと、
将来は佐藤姓だけになるのでは」との仮説をたて、検証した。
算出方法は23年の人口における佐藤姓の占有率を1.53%とし、
これに22~23年の伸び率1.0083を掛ける計算を繰り返した。
姓の増減には、結婚や離婚、出生、死亡などの影響が反映されるという。
すると2446年に国内人口における佐藤姓の占有率が50%を超え、
2531年に100%に達したとのことです。
なぜ日本では夫婦別姓が認められていない?
「氏(うじ)」とは「氏族」と呼ばれる血縁集団を表し、
各氏族には王権の中で担当する職務が定められていました。
古代の大王家(天皇家の前身)を中心としたヤマト王権では、
その氏族を「氏」と呼んで管理し、氏族もその氏を名乗っていました。

「姓(かばね)」は、元々は古代の大王家が氏族に与えた「称号」のことをいい、
臣(おみ)、連(むらじ)、伴造(とものみやつこ)、国造(くにのみやつこ)等があります。
「姓(かばね)」は“天皇から授かる”呼び名、称号のことでした。
古代の日本では「氏(うじ)」は血縁集団の呼び名のこと、
「姓(かばね)」は天皇が与えた称号のことだったので、
「名字」とは異なるものでした。
明治時代に入ると国民に氏(姓) が与えられ、
1898 年、明治民法において、
「戸主及び家族はその家の氏を称する、妻は婚姻に 因りて夫の家に入る」と
公布・施行されたこと により、夫婦同氏(姓)であること、
妻が夫の 氏(姓)を名乗る習慣が日本に定着し ていきました。
日本で夫婦別姓が実現しない背景は、
所謂「イエ制度」の考え方が残っていることや、
別姓にすると家族の一体感が薄れると危惧されているためといわれています。
結婚したら女性は婚家のもの、という考え方が強く根付き、
夫婦同姓制度は、夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない別姓制度よりも、
より絆(きずな)の深い一体感ある夫婦関係、
家族関係を築くことのできる制度であると言われています。
夫婦別姓を選択するデメリット。
選択的夫婦別姓制度の問題点として、
相続や公的サービスにおいて法律上デメリットが生じることがあります。

例えば、
・お互いに法定相続人になることができない(=配偶者として遺産を受け取ることができない)
・所得税の配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇が受けられない
・配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除が受けられない
・夫婦間に代理権がなく、配偶者の代理人として契約することができない
といったデメリットが挙げられます。
もう1つのデメリットとして、
「子どもの姓をどうするべきか、選択が難しい」というものがあります。
夫婦に子どもが生まれたとき、
夫婦が同姓である場合は子どもも必然的に同じ姓を名乗ることになります。
しかし、夫婦が別姓である場合、
子どもにどちらの姓を名乗ってもらうのかは大きな論点になります。
アメリカでは夫婦別姓OKですが、
みんながみんな別姓にするかというとそういう訳でもないようです。
結婚の際に同じ名字にする人もいれば、
二つの名字をハイフン(-)でくっつける人もいます。
または、夫婦別姓でも、子供に名付ける時に
二人の名字をハイフン(-)でくっつけたりというのも見られるようです。
これを日本で導入したら…「佐藤―田中太郎」くんと言うことになるのでしょうか。

面白いことに、日本は外国人と結婚した時のみ、別姓はノー・プロブレムなのです。
姓の在り方を考える時が来た
婚姻の際に夫婦別姓も選べるよう法改正を求める訴訟が起きています。
2011年に始まった夫婦別姓訴訟で原告団副団長を務めた小国香織さんは、
「自分の名前」を失うことの意味が軽んじられている、と指摘します。
「名字も自分の名前」であり「名前を変えたくない」という
本質的な部分が十分には理解されていないことが大きいように感じるとのことです。
確かに、改姓を喜ぶ人もいれば、
「同姓でも別姓でも、どちらでもいい」と考えている人もたくさんいますし、
「体を傷つけられる」とか「自分がなくなる」と比較されてしまうほどの
苦痛を感じてしまう人もいます。
自分の名前を失うことの重大さは、軽んじられてしまいます。
この試算は期間も長すぎるため、不確実な要素も多く、
そもそもこの試算には、
佐藤さんという姓の女性と田中さんという姓の男性が結婚し、
佐藤さんを名乗る、というケースが含まれていないような気がします。
これを理由に『だから夫婦別姓の方がいい』という根拠にはならないと思います。
むしろ、このまま少子化が続けば、
約500年後に日本という国があるか否かの方が怪しいです。
約500年後には…佐藤じゃなく王とか張とか李になってたりして。
今日のヒメちー
今日もねぇやんはなかなかにぶっ飛んでいますね。

猫には姓と言うものは多分ですがありません。
そもそも名前だってあるのかどうかわかりません。
もし名前があるのだとして…。
ヒメのママがヒメのことを「エリザベスちゃん」と呼んでいたとしましょう。
ここのおうちの子になって「ヒメ」「ヒメちー」、
「ヒメちゃん」「ヒメチョコラビッチ」「メーちゃん」と呼ばれるようになった時、
ヒメはヒメのママから与えられた名を奪われたことになります。

けれどそれでいいのです。
「エリザベス」にも「ヒメ」にも
どちらにもヒメに対する愛が含まれているのですから。

名なぞしょせん記号。

うまくまとまったところで、
ヒメはお昼寝に入らせていただきます。
アディオース!

わたし、ねぇやんの姓は「絶滅危機」とまではいかなくても珍しい苗字。
姓+名は日本に一人しかいません。
うちでは、ぱぱちゃんもままちゃんも姓にこだわらないので
とやかく言われることはありませんが、
わたしが生まれたとき、ぱぱちゃんのおじいちゃんは
姓を残すために「男の子を産め」と言ったそうです。
結局はわたしもいもーとも女でしたが。
『姓』にこだわりたい人、こだわらなくていい人。
どちらの希望も叶う未来になるといいね。



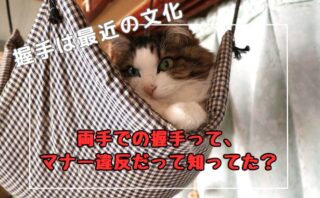








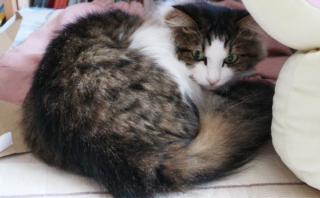

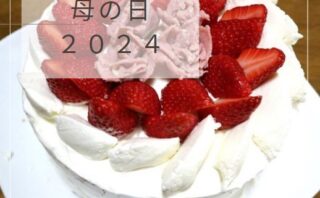

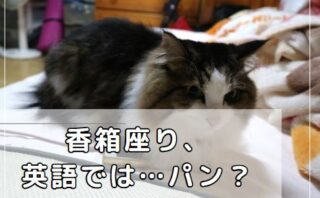





コメント