
『認知的不協和』に陥っているZ世代
環境問題に際してZ世代の53%、ミレニアル世代の50%が
「自身の購入が環境に与える影響を理解したい」と考えているものの、
必ずしも環境配慮型の製品を選んでいるわけではない、という調査結果があります。
わたしはZ世代ではありませんが、非常に興味がある内容でした。
認知的不協和(にんちてきふきょうわ、英: cognitive dissonance)とは、
人が自身の認知とは別の矛盾する認知を抱えた状態、
またそのときに覚える不快感を表す社会心理学用語です。
アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱されました。
人はこれを解消するために、矛盾する認知の定義を変更したり、
過小評価したり、自身の態度や行動を変更すると考えられているものを差します。
有名な例として、イソップ物語のキツネとすっぱい葡萄と言うお話があります。
あるところに、一匹のキツネがいました。
しばらくの間、何も食べておらず、とてもお腹が空いていました。
歩いていると、目の前に葡萄畑がありました。
たわわに実った、おいしそうな葡萄がなっています。
腹ペコのキツネは、背伸びをしたり、ジャンプしたりして、
何とか葡萄を食べようとしました。
ところが、葡萄は高いところになっていて、
どうしても、葡萄を採ることができませんでした。
諦めたキツネは、立ち去りながら、恨めしそうにつぶやきました。
「どうせ、あの葡萄は酸っぱいに違いない。誰が食べるものか」
と言うもの。
端的に言うと「負け惜しみ」と言うことになります。
矛盾する認知によって生じる心理的ストレスとも表現されます。
不協和の存在は、その不協和を低減させるか除去するために、
とる行動・言動であると言えます。
複数(通常は二つ)の要素の間に不協和が存在する場合、
一方の要素を変化させることによって不協和な状態を低減、
または除去するという心理的な仕組みです。
例えばあるコミュニティで何らかの災害が発生していると、
その災害が起こっていない隣接するコミュニティで、
不合理な恐ろしい噂が広がる。

これは、脅威に直面していない人が、
災害への不安を正当化する必要があるためである 、と言われています。
このままではいけない、と分かってるのに実行に移せない不協和
よく挙げられる例として、「喫煙者」の不協和があります。
| 喫煙者が喫煙の肺ガンの危険性(認知2)を知る | |
|---|---|
| 認知1 | 私、喫煙者Aは煙草を吸う |
| 認知2 | 煙草を吸うと肺ガンになりやすい |
このとき、認知1と認知2は矛盾する。
「肺ガンになりやすい」ことを知りながら、「煙草を吸う」という行為のため、
喫煙者Aは自分自身に矛盾を感じる。

そのため喫煙者Aは、認知1と認知2の矛盾を解消しようとします。
| 自分の行動(認知1)の変更 | |
|---|---|
| 認知3(認知1の変更) | 私、喫煙者Aは禁煙する |
| 認知2 | 煙草を吸うと肺ガンになりやすい |
一番論理的なのは認知1を変更すること。
「喫煙」を「禁煙」に変更すれば、
「煙草を吸うと肺ガンになりやすい」と全く矛盾しなくなります。
これが小さなことならば、
自分の行動を修正または変更することで解消することができます。
例えば、漢字を間違って覚えていたならば
正しい漢字を覚えなおせばよい、というように。
けれど、喫煙の多くはニコチンに依存する傾向が強いため、
禁煙行為は苦痛を伴う。
したがって、「喫煙」から「禁煙」へ行動を修正することは多大な困難が伴い、
結局は「禁煙」できない人も多い。
その場合は、認知2に修正を加える必要が生じてくる。
| 新たな認知(認知4または認知5)の追加 | |
|---|---|
| 認知1 | 私、喫煙者Aは煙草を吸う |
| 認知2 | 煙草を吸うと肺ガンになりやすい |
| 認知4 | 喫煙者で長寿の人もいる |
| 認知5 | 交通事故で死亡する確率の方が高い |
「喫煙者で長寿の人もいる」(認知4)を加えれば、
「煙草を吸う」(認知1)と
「肺ガンになりやすい」(認知2)との間の矛盾を弱めることができる。
そして「交通事故で死亡する確率の方が高い」(認知5)をつけ加えれば、
肺ガンで死亡することへの恐怖をさらに低減することができる。

この主張は「煙草を吸うと肺ガンになりやすい」(認知2)を変化させることで、
認知的不協和状態を解消させようというものでありますが
結局は屁理屈をこねて自分を正当化させようとする認知的不協和なのですね。
少し難しくなりましたが、
認知的不協和(cognitive dissonance)とは、
自身の思考や行動と矛盾する認知を抱えている状態、
またその際に覚える不快感を意味する言葉です。
簡単に身近な例を挙げると、
「ダイエットしたい」と

「カロリーが高いものを食べたい」という矛盾する認知が、

ストレスになっているような状態を指します。
Z世代じゃなくても十分感じてるわ…。
今日のヒメちー
春がそこまでやって来てるのは分かっているのですが…。

この暖かいベッドから、動きたくありません。

いつまでも電気使っていてよいものか、と

寒いのだから電気の力で温まって当然だ、という矛盾ですね。

ねぇやんの気持ちが少しだけわかる気がしますよ。

痩せるためには食べちゃいけない。
でも食べたい。
ここまでが矛盾。
食べても運動すればいいのよー、と言うのが認知的不協和ですね。

ふっ。
人も猫も、
Z世代もゆとり世代も、おんなじですね。

太りたくないならば食べなければいい。
それは分かってるし、事実なのだけれど、つい食べちゃう。
人は矛盾と不協和のストレスと、戦って生きているのかも

















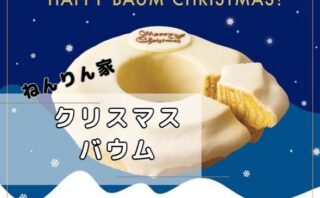





コメント