
ライオンの尾より猫の頭になるほうがいい(または犬の頭)。
紳士の国、イギリスにはこのようなことわざがあります。
「better be the head of a cat than the tail of a lion」
または
「Better to be the head of a dog than the tail of a lion」
この言葉は、直訳すると
「ライオンの尻尾となるよりは、猫(犬)の頭となった方がよい。」という意味になります。
え?ライオンのしっぽ?

これは日本で有名な「鶏口となるも牛後となるなかれ(中国のことわざ)」、
「鶏口牛後」と同じ意味で、
どちらも「大きな集団の末端となるよりは、
小さな集団の長となる方が良い」ということを表しています。
意味は同じでも、使われている動物が違いますね。
百獣の王、ライオンを崇敬する国、イギリス
人間の文化において、ライオンは力や勇気、強さ、騎士道などの象徴となっています。
イギリスの国獣はライオン。
イングランド王室紋章としても知られています。

盾の中に2組配された金色のライオン。 3頭はイングランド王室紋章。
ライオンはイングランド王家の紋章を、ユニコーンはスコットランドの紋章、
竪琴はアイルランドの紋章。
盾の上には、冠をかぶったライオンがいる。
ライオンのかぶっている冠は、イギリスの代表的な冠で、
このライオンはイギリスを守っている、という意味があるそうです。

サッカーイングランド代表のマークはこれを元に、
イングランドの国花のバラをあしらったもの。

最も象徴的な紋章学上の動物として知られている「イングランドのライオン」ですが、
その起源は少なくとも12世紀にさかのぼり、
以降王室の盾の紋章の一部分として常に別格の扱いを受けて来ました。

なるほど、ことわざにも登場するわけですね。
「鶏口牛後」の由来
「鶏口牛後」の由来は『史記』の中の「蘇秦伝」です。
戦国時代策士の1人、蘇秦は秦以外の6ヶ国「韓・魏・趙・楚・燕・斉」の王に対して、
秦に従うのではなく独立国として
各国が合従連衡して秦に対抗するべきだと説いてまわりました。
これは6ヶ国に同盟を組ませることで秦の力を抑え侵略行為を妨げるためでした。
その時、蘇秦が韓の宣恵王に述べた言葉が
「寧(むし)ろ鶏口と為るとも、牛後と為ること無かれ」で、
ここから「鶏口牛後」が生まれました。

蘇秦は同盟に消極的だった韓の王に
「大国の秦の臣下となるなら、牛の尻になることとなんら変わりありません。
それなら小さくても一国の王であったほうがいい」と説き、
誇り高き韓の王はこの合従策を受け入れ同盟が成立したのです。
「鶏口牛後」は、受験、就活や転職の話題のなかでよく使われる言葉ですね。

「鶏口となるとも牛後となるなかれ」という形で用いられることも多く、
人生の岐路に立つ人へのアドバイスとしても使われます。
他にも「鯛の尾よりも鰯の頭(北朝鮮)」、「大鳥の尾より小鳥の頭(不明)」、
「虎のしっぽになるより、蝿(はえ)の頭になれ。(モンゴル)など、
同じ意味をもつことわざは複数存在します。
全て同じ意味にもかかわらず、
ここまで多くのバリエーションが存在するとは驚きですね。
多くの人々にとって共感できる教訓だったからこそ、
これほどまでに多くのバリエーションが生まれたのだといえるでしょう。
今日のヒメちー
ことわざって人が作るんですよね?

ふっ
尻尾がない人間にはしっぽの重要さが分かっていませんね。

尻尾はまず猫にとって可愛い部位でもありますし―。
バランスをとったりするためにも必要なのですよ。

多くは語らなくともしっぽが語ってる、と言う場合もありますしね。
このように、ねぇやんに嫌がらせをするのだってお茶の子さいさいです。

ねぇやんもねー、このことわざ知ったのって確か中学生くらいの時だったんだけど、
例えば東大のビリの人と、
ニッコマのトップの人ってどっちが優秀なのかしら、とか、
社会的にはどっちが有利なのかしら、とか考えた物よ。
あ。もちろん、人の能力は学歴がすべてじゃないってことは踏まえてね。
しっぽが重要な部位じゃないって発想、
きっとしっぽのあるペットと暮らしてなかったひとが作ったのよね。

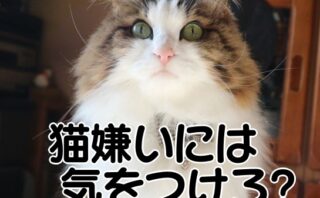



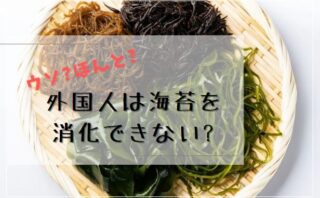




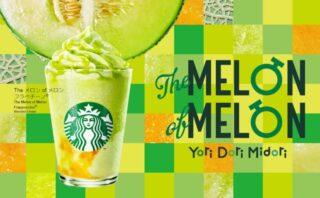











コメント